情報の宝庫!キュレーションサイトのメリットと運営の注意点まとめ
2021年4月7日
東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!
SEOがまるっと解るWebマガジン
更新日:2025年 02月 21日
 コンテンツSEOとは?初心者でも実践できる効果的な方法と成功のポイント
コンテンツSEOとは?初心者でも実践できる効果的な方法と成功のポイント

【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者
栗原 勇一
SEOに関わりのある方なら、「コンテンツSEO」という言葉を聞いたことはあるかと思います。
一昔前であれば、被リンクの数やページ内のキーワード数など、質よりも量で評価されておりました。しかし2011年のパンダアップデートや2012年のペンギンアップデートの影響により、これまで”量”を評価していたGoogleが、質を重要視する傾向に変わりました。
GoogleのアップデートとともにSEO対策の手法や取り組み方にも変化が生まれはじめ、近年、注目されるようになったのが「コンテンツSEO」です。
この記事では、コンテンツSEOとは何なのか、どのような対策を取れば良いのかを中心に解説していきます。
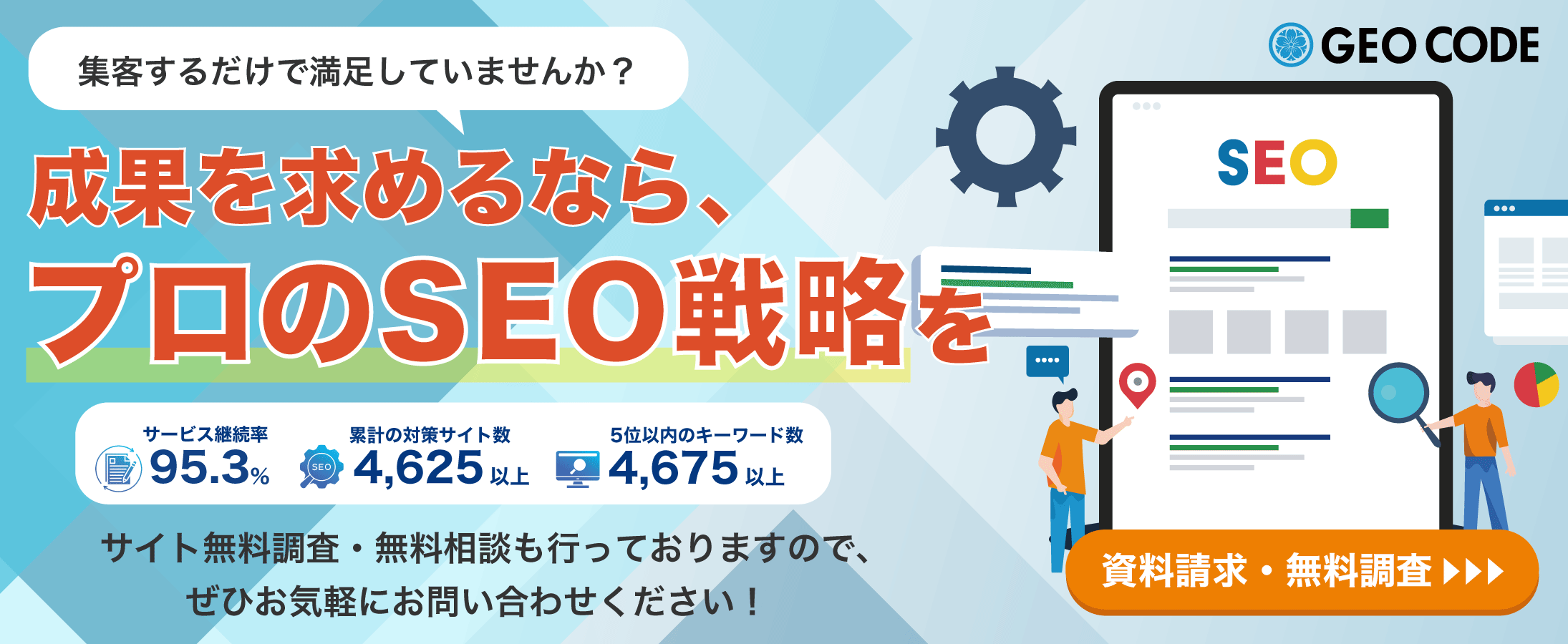

目次
コンテンツSEOとは、SEO対策の手法の一つであり、サイト上のコンテンツを活用し、多様なキーワードでの露出機会の増加を実現することで、多くの有益なアクセスを集める集客施策です。
検索結果の上位に表示されるための要素として、コンテンツが注目されるようになった背景には、前述のパンダアップデートやペンギンアップデートを含めた様々なGoogleのアップデート、Googleクローラーの性能が向上したことが大きく関係しています。
当時はこれらの影響により、被リンクを大量に設置しているサイトや、コピーコンテンツ、キーワードを不自然に詰め込んだページの順位が下落しました。反対に、ユーザーのニーズを網羅したWebページは順位が上昇しました。
Googleクローラーの性能が高くなり、文章の内容や文脈をこれまで以上に理解できるようになったことでコンテンツの質が注目されるようになりました。
現在、多くの企業がWebサイトを活用して集客を行っています。しかし、単にサイトを持っているだけでは、ターゲットユーザーに情報を届けることはできません。では、どうすれば自社サイトを通じて効率的に集客できるのでしょうか?
その答えが「コンテンツSEO」です。コンテンツSEOでは、検索エンジンだけでなくユーザーにとって有益な情報を提供することを最優先に考えます。その結果、以下のようなメリットが得られます。
このように、コンテンツSEOは「ただ検索結果の上位を狙う施策」ではなく、「ユーザーに価値を提供し、結果的にSEOにも好影響を与える手法」なのです。
コンテンツSEOと従来のSEOは、どのような違いがあるのでしょうか?以下の表にまとめました。
| 項目 | 従来のSEO | コンテンツSEO |
|---|---|---|
| 目的 | 検索順位を上げることが主目的 | ユーザーに価値を提供し、結果的に検索順位を上げる |
| 手法 | キーワード最適化・被リンク獲得 | ユーザーニーズに基づいたコンテンツ制作 |
| 評価基準 | キーワードの出現頻度やメタタグ最適化 | E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を考慮 |
| 効果の持続性 | 短期的(アルゴリズム変更の影響を受けやすい) | 長期的(質の高いコンテンツは安定した流入を生む) |
従来のSEOでは、「検索エンジン向け」の施策が中心でしたが、コンテンツSEOでは「ユーザー視点」が軸となるのが最大の違いです。
たとえば、かつては「ターゲットキーワードをページ内に何度も出現させる」ことで検索順位を上げることができました。しかし、現在のGoogleはユーザー体験を重視するアルゴリズムを採用しており、不自然なキーワードの多用は逆に評価を下げる要因になります。
これからのSEO施策では、ユーザーが本当に求めている情報を提供し、自然な形で検索エンジンにも評価されるコンテンツ作りが重要になります。コンテンツSEOを正しく活用することで、企業のWebサイトは「検索エンジンにとっても、ユーザーにとっても価値のある存在」となり、持続的な集客が可能になります。
Googleクローラーの性能は日々向上していますが、人間と同じようにコンテンツの内容を理解しているわけではありません。
Googleクローラーはソースコードやタグの情報などを総合的に評価しているため、コンテンツをWebサイトに公開する際は、Googleに対してのコンテンツの質、ユーザーに対してのコンテンツの質を意識する必要があります。
Googleに対してのコンテンツの質、つまり中身の情報をGoogleクローラーに正しく読み取ってもらう、理解してもらうためには、HTMLソースコード、タグなどの設定を意識することが重要です。
大きく分けると以下の5つのポイントがあります。
これは、Googleクローラーがコンテンツの中身だけではなく、ソースコード上に書かれている情報も読み取りながらページを評価するためです。
同じ内容が書かれているページであっても、ソースコード上での設定が違うだけでGoogleからの評価も変わってきます。コンテンツSEOを実施する際はコンテンツの中身だけではなく、Googleに対しての質も意識しましょう。
ユーザーに対してのコンテンツの質とは、簡単に言ってしまうとユーザーニーズを満たすコンテンツを用意することです。曖昧な表現になってしまいましたが、この一言に尽きます。
どのようなキーワードに対してコンテンツを作成していくかというキーワード選定や、「このキーワードで検索するユーザーはこういった情報を欲しているだろう」といった検索キーワードに潜んだ検索意図の把握と、その答えとなるコンテンツ作りが重要になります。
当然、文章の読みやすさやコンテンツそのものの構成も重要ですが、ユーザーニーズ・検索意図を満たしていないコンテンツは、残念ながら質が高いとは言えません。
では、ここでコンテンツSEOを実施した場合のメリットを考えていきましょう。
コンテンツSEOにはさまざまなメリットがありますが、特に「集客効果の安定」「費用対効果の高さ」「ブランディング向上」に加えて、「リード獲得の強化」や「長期的な資産価値」という点が大きな魅力です。
この5つのメリットを詳しく解説していきます。
コンテンツSEOに限らずSEO対策全般に言えることですが、各キーワードでの上位表示が叶うことや、検索結果へ表示されるキーワードが増えることによって検索ユーザーへの露出機会が高まるため、高い集客効果が見込めます。
検索結果の1位に表示された場合のクリック率は約39.8%、2位の場合は約18.7%ですが、10位の場合は1.6%まで下落します。
2025 Click-Through Rates (CTR) by Google Ranking Position
Google Search Feature CTR Search Position 1 39.8%* Search Position 2 18.7%** Search Position 3 10.2% Search Position 4 7.2% Search Position 5 5.1% Search Position 6 4.4% Search Position 7 3.0% Search Position 8 2.1% Search Position 9 1.9% Search Position 10 (if present) 1.6% If snippet, then 42.9%; If AI overview, then 38.9%; If local pack present, then 23.7%
引用: Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025 – First Page Sage
** If snippet, then 27.4%; If AI overview, then 29.5%; If local pack present, then 15.1%
このことからも、上位表示された場合の集客力が強いことが分かります。
また、ユーザーニーズ・検索意図を満たした質の高いコンテンツは、質の低いページよりもアップデートによる順位変動を受けずらいため、永久にとはいかないものの、安定かつ継続的な集客が期待できます。
コンテンツSEOは一回実施して終わりというものではなく、継続的に質の高いページをWebサイト上に公開していくことが重要です。
コンテンツの母数が増えるほど、検索結果に表示されるキーワードの増加に繋がり、さらなる集客効果の向上も期待できます。
質の高いコンテンツを増やすことができればサイト全体のGoogleからの評価アップにも繋がり、様々なキーワードでの上位表示や検索結果での露出機会の向上が期待でき、有益なキーワードからのアクセスが増えることでCV(コンバージョン)の獲得も望めます。
リスティング広告などはクリック数に応じた費用が発生し、単価の高いキーワードであれば1クリック1,000円を超えるものも珍しくありません。ですが、コンテンツSEOは自然検索枠に表示されるため、何回クリックされても費用がかかりません。
コンテンツを自社で作成することができれば、人件費以外の費用がかからずに実施できるのもコンテンツSEOの魅力です。
上位表示されるまでに時間がかかる場合もありますが、ビッグキーワードや自社のビジネスに直結するキーワードで上位に表示させることができれば、費用対効果は極めて高いです。
質の高いコンテンツを継続的にアップすることにより、他サイトからの被リンクの獲得やSNSでの拡散が期待できます。
様々なキーワードで上位に表示されることに加え、多くのサイトからリンクされたり、SNS上で話題になることで、Web上で人に目に触れる機会が増え、潜在顧客の獲得や自社ブランディングの向上に繋がります。
また、コンテンツを継続的に多数発信し続けることもブランディングに繋がります。
ユーザーが検索したキーワードに関連したコンテンツだけを用意しているサイトよりも、それに不随する情報をたくさん用意しているサイトの方がユーザー満足度は高くなります。
例えば、「部屋の照明」を検索しているユーザーに対して、「おすすめの照明」だけ掲載されているサイトよりも、「男女別のおすすめ照明」や、「部屋の広さ別のおすすめ照明」などのコンテンツが用意されているサイトの方が、ユーザーからも信頼されブランディングに繋がります。
ブランディングが高まることにより、成約率の改善や受注単価の向上など、企業としての売上拡大に繋がるメリットも期待できます。
ブランディング向上のため、企業として信頼されるコンテンツの発信を心掛けましょう。
コンテンツSEOは単なる集客施策にとどまらず、リード獲得や問い合わせの増加にも大きく貢献します。質の高いコンテンツを提供し、検索ユーザーの課題を的確に解決することで、「この企業なら信頼できる」「もっと詳しく話を聞きたい」という心理的な動機を生み出すことが可能です。
例えば、以下のような流れでユーザーが問い合わせに至るケースが考えられます。
課題を抱えたユーザーが検索し、貴社のコンテンツに辿り着く
↓
記事を読むことで、自分の課題が整理され、解決策の方向性が見えてくる
↓
「この会社は専門的な知識が豊富そう」と信頼を持つ
↓
「プロに相談したほうが早いかもしれない」と感じ、問い合わせや資料請求をする
特に、BtoBマーケティングでは「今すぐ問い合わせたい!」と強く思っているユーザーだけでなく、情報収集段階のユーザーにもリーチし、中長期的にリードを育成することが重要です。
そのため、コンテンツ内に問い合わせフォームへの導線を適切に設計することがポイントになります。以下のような施策を組み合わせることで、リード獲得率の向上が期待できます。
コンテンツSEOは、単に「検索結果の上位に表示される」ことがゴールではなく、ターゲットユーザーとの信頼関係を築き、問い合わせへと導く手段としても有効なのです。
コンテンツSEOの大きな魅力の一つは、一度作成したコンテンツが長期間にわたって集客し続ける「資産」になるという点です。
リスティング広告などの有料施策は、広告費を投下している間は即効性のある集客が可能ですが、予算が尽きると一気に流入がストップしてしまいます。それに対して、コンテンツSEOは一度検索上位に表示されれば、継続的に流入を生み出し続けることができます。
また、コンテンツはリライトや更新を重ねることで価値を維持しやすいのも特徴です。
こうした運用を続けることで、コンテンツの価値を高め、長期的に集客し続ける仕組みを作ることができます。
また、サイト内に蓄積されたコンテンツが増えることで「情報が豊富なサイト」としてGoogleからの評価も向上し、サイト全体の検索順位が底上げされる効果も期待できます。
コンテンツSEOは短期間で結果が出る施策ではありませんが、一度軌道に乗ると安定した集客基盤を築くことができるため、長期的な視点で取り組む価値が大いにある施策です。
このようなメリットを獲得するために、押さえておくべきコンテンツSEOの重要な対策を紹介します。
コンテンツSEOのみならずSEO対策全般に当てはまりますが、以下に記載されているGoogleの理念は常に意識してコンテンツの作成をしましょう。
1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。
引用: Google が掲げる 10 の事実
コンテンツSEOは、短期的な効果を見込んだ対策ではありません。そのため、長期的な視点で数多くのコンテンツを作成していくことが、成功を収める重要なポイントです。
また集客効果を最大化をさせるためにも、コンテンツの数は大切です。
質の高いコンテンツを多く作成し、Webサイトへのアクセスを増やしましょう。
Googleは「検索品質評価ガイドライン」の中で、独自性のあるコンテンツの重要性を強調しています。
作成したコンテンツの中に他サイトからコピーした情報が含まれている場合、ユーザーの信頼を損ねるだけでなく、Googleの評価も下がる可能性があります。
反対に、専門的な知識や自社の独自データを活用したオリジナルコンテンツを作成することで、検索エンジンから高く評価され、検索順位の向上が期待できます。
また、単なる情報の羅列ではなく、自社の視点やユニークな切り口を加えることも重要です。例えば、業界の最新トレンドを踏まえた分析や、読者が実践しやすいアクションプランを提示することで、価値のあるコンテンツを作ることができます。
「他では得られない情報」を意識してコンテンツを作成し、ユーザーにとって有益なコンテンツを目指しましょう。
コンテンツSEOにおいて、Googleの評価基準として重要視されるのがE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)です。これは、Googleが「質の高いコンテンツとは何か?」を判断するための指標であり、検索順位にも大きな影響を与えます。
特に、健康・金融・法律などのYMYL(Your Money or Your Life)領域に関するコンテンツでは、E-E-A-Tが重要視される傾向がありますが、それ以外の分野でもユーザーに信頼される情報を提供するために不可欠な要素です。
E-E-A-Tを高めるためのポイント
E(Experience:経験)
実際に経験したことや、ユーザーの体験談を交えたコンテンツは、信頼性が高まります。自社の事例やユーザーの成功体験を積極的に取り入れましょう。
E(Expertise:専門性)
記事のテーマに関する専門知識を持った人が書いているかが評価されます。専門家の監修を入れる、業界のデータを引用するなど、客観的な根拠を示しましょう。
A(Authoritativeness:権威性)
コンテンツの発信元の信頼性も重要です。企業としての実績や、過去の成功事例、他メディアでの紹介歴などをコンテンツに盛り込むことで、権威性をアピールできます。
T(Trustworthiness:信頼性)
事実に基づいた正確な情報を提供し、誤解を招かないようにすることが大切です。情報ソースの明示、著者情報の掲載、HTTPS対応のWebサイト運用なども、Googleの評価を高めるポイントになります。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りを実践することは、検索順位の向上だけでなく、読者からの信頼獲得にもつながるため、長期的なWebマーケティング戦略においても重要な要素となります。
最後に、これまでの情報を踏まえた上でコンテンツの作り方をご紹介します。
成果を出すためには、自社商品やサービスの分析が不可欠です。
まずは自社商品やサービスをしっかりと理解し、ターゲットを選定しましょう。
この時点ではキーワードを選定する必要はありません。
1の分析結果から、自社商品やサービス、ターゲットにマッチするキーワードを選定しましょう。
出てきたキーワードをGoogleのキーワードプランナーを使い検索ボリュームを調べます。
検索ボリュームが極端に少ないキーワードは見落としがちですが、直接購買に繋がるキーワードや、見込み顧客を引き込めるキーワードの場合は残しておきましょう。
検索ボリュームに惑わされずにキーワードを選定することが重要です。
選定したキーワードで実際に検索をします。
その際に、検索結果の上位10位内にどのようなページが表示されているかを注意してみてください。
コラムなどのコンテンツ系のページが多く表示されている場合は良いですが、サービスページやコーポレートサイトが表示されている場合は、Googleはそのキーワードに対してはサービスページなどを上位表示させる傾向があることが分かります。
検索結果の上位に、コンテンツ系のページが少ないキーワードは除外しましょう。
3で絞られたキーワードで上位に表示されているページの内容を確認します。
できれば1位から10位までは全て確認し、内容を洗い出しましょう。
内容を洗い出すことにより、多くのページで共通して記載されている情報が見つかると思います。
その情報が、ユーザーが求めている情報であり、Googleが評価している情報の可能性が高いため、可能な限りピックアップしましょう。
また、ここでは各ページの文字数を調べておきましょう。
4でピックアップしたコンテンツをまとめる作業に入ります。
記事としての構造や、文章としての構造がおかしくならないように注意しましょう。
対策キーワードで上位に表示されているページの文字数を参考に、コンテンツの構成を考えましょう。
また、ここで一番重要なことはオリジナルのコンテンツを盛り込むことです。
ピックアップしたコンテンツ以外にも、ユーザーはこの情報も欲しいのではないかと仮説を立てて、最終的な構成を作成します。
ここまでできれば後は構成に沿って文章を書くだけになります。
ユーザーが読みやすいようにライティングできているかを意識しましょう。
また、誤字や脱字にも気を付けましょう。
Webサイトにアップする際は、適切なカテゴリやページに追加することが重要です。
また、Googleに正しく評価されるための基本的なSEO設定(タイトルタグ、メタディスクリプション、hタグの設定など)を忘れずに行いましょう。
アップ後の効果測定や改善については、「アップ後の効果測定と改善の重要性」で詳しく解説しますので、そちらも参考にしてください。
コンテンツSEOは、記事をアップしたら終わりではなく、継続的な分析と改善が不可欠です。どんなに良いコンテンツでも、実際にどのような成果を出しているかを把握しなければ、効果を最大限に引き出すことはできません。
① アップ後の効果測定
GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを活用し、以下の指標を定期的にチェックしましょう。
② 改善のポイント
効果が思うように出ていない場合は、以下のようなアプローチで改善を行いましょう。
コンテンツの価値を最大化するためには、「作って終わり」ではなく、データを基に改善を繰り返すことが重要です。
コンテンツSEOを成功させるには、検索エンジンの評価基準を理解しつつ、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが重要です。
ここでは、コンテンツSEOの成果を最大化するためのポイントを紹介します。
検索エンジンで上位表示を狙うためには、ユーザーが何を求めているのかを理解し、それに応えるコンテンツを作成する必要があります。
検索結果を分析する
→ 狙っているキーワードで検索し、上位10記事の共通点を探る
→ 記事の形式(ブログ記事、比較記事、リスト型記事など)を把握する
ユーザーの悩みを解決する内容にする
→ 例えば「SEO対策とは?」というキーワードなら、「初心者向けの基礎知識+具体的な手順」を含めると検索意図を満たしやすい
コンテンツSEOは作って終わりではなく、改善し続けることが重要です。
Googleは、最新の情報が反映されたページを高く評価する傾向があるため、定期的な更新を行いましょう。
SEOを意識しすぎるあまり、キーワードを詰め込みすぎたり、不自然な文章になったりすると逆効果です。
ユーザーがストレスなく読み進められるように、以下の点を意識しましょう。
Googleの検索アルゴリズムは、単なるキーワードの多さではなく、ユーザーにとって役立つかどうかを重視しています。
「このコンテンツを読んで、ユーザーは本当に満足できるか?」という視点でチェックしましょう。
コンテンツSEOは、すぐに成果が出るものではなく、長期的に取り組むべき施策です。
Googleの公式見解によると、SEOの効果が出るまでには4ヶ月~1年かかるとされています。
参考:Google Search Central
一般的に、適切なコンテンツ制作と運用を続けた場合、3ヶ月〜6ヶ月で検索流入が増え始めるケースが多いですが、競争が激しいキーワードでは1年以上かかることもあります。
よくある失敗:
キーワードの意味を正しく理解せず、ターゲットと異なる内容を書いてしまう
競合記事と比べて、ユーザーの知りたい情報が不足している
回避策:
検索結果の上位記事を分析し、共通点と差別化ポイントを把握する
このキーワードで検索する人は、何を知りたいのかを考えて記事を設計する
よくある失敗:
一度記事を公開したら、そのまま放置してしまう
検索順位が落ちているのに、リライトをしていない
回避策:
定期的にGoogleサーチコンソールで順位を確認する
検索意図の変化に合わせてコンテンツをアップデートする
よくある失敗:
キーワードを不自然に詰め込みすぎてしまう
長文すぎて、途中で離脱される
回避策:
見出しや箇条書きを活用し、視認性を高める
キーワードの多さではなくユーザーにとって役立つかを基準にライティングする
コンテンツSEOは、検索エンジンの評価を意識しながら、ユーザーにとって有益な情報を提供することで、安定した集客を実現できる施策です。
本記事では、コンテンツSEOの基本から、成果を出すための具体的な方法、よくある失敗とその回避策までを解説しました。
この記事のポイント
コンテンツSEOは「一度作って終わり」ではなく、「継続的な改善」が成功のカギです。
検索順位やアクセス解析のデータを定期的にチェックしながら、必要に応じてリライトを行いましょう。
もし、「どんなコンテンツを作ればいいかわからない」「コンテンツSEOの施策を効果的に進めたい」とお悩みの方は、ぜひジオコードにご相談ください!
ジオコードでは、SEOのプロがコンテンツ戦略の立案から記事制作、効果測定・改善までトータルでサポートします。